
- 入居時
- 0 円 ~ 880 万円
- 月額
- 24.64 万円 ~ 39.31 万円
お客様相談室に繋がります
- ※営業時間外は、お電話がつながらない場合がございます。
- ※お電話の際はオアシス介護を見た旨を必ずお伝えください。
- ※上記電話番号はIP電話・ひかり電話からご利用出来ません。携帯電話・スマートフォンよりご利用ください。
138件
エリア
板橋区
費用・医療・条件
未選択
施設種類
未選択

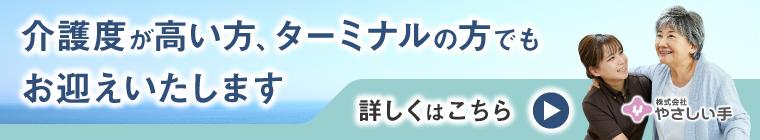

【標準サービス】 ■駆け付けサービス ◎警備会社ガードマンが駆けつけます。 ・24時間365日対応の緊急通報システム。体調の急変時などにボタンを押せばガードマンが駆けつけます。 ◎生活リズムの変化をセンサーが見...

【■駆け付けサービス】【標準サービス】 ■駆け付けサービス ◎警備会社ガードマンが駆けつけます。 ・24時間365日対応の緊急通報システム。体調の急変時などにボタンを押せばガードマンが駆けつけます。 ◎生活リズム...







【◆◇見学・入居申込受け付けております!土日見学可能です。◇◆】サービス付き高齢者向け住宅「ディーフェスタ西台」は、面会制限なし! ご自身で身の回りの事ができる方はもちろん、要介護3~5の常に医療や介護が必要な方...

【■■設備が充実した居室■■】「ニチイホーム板橋徳丸」では、居室にナースコールが完備。 そのほか、介護用電動ベッド(寝具付)・温水洗浄機能付トイレ・洗面台(車いす対応)・エアコンといった生活に欠かせない設備か...


【相談員による月1回の面談、安心安全を叶える設備が連携】■駆けつけサービス 生活リズムの変化をセンサーが見守り、緊急時には警備会社ガードマンが駆けつけます。 ■看護師による健康相談(電話) 365日24時間、相談ボ...

【このホームのみどころ】■ポイント1 :池袋から東武東上線で14分の利便性に優れた好立地 ■ポイント2 :施設周辺には図書館や公園、農園が多く、外出や散歩を楽しむ事ができます。 ■ポイント3 :定員35名の家庭的な雰...




【■生活リハビリに特化した住まい!】機能訓練指導員(理学療法士)がご入居者様お一人おひとりに合わせ、リハビリを計画・実施しています。 また「ドーミーときわ台」では、身体機能や認知機能の維持を目標に、身体を動か...

【■認知症ケアの専門スタッフが丁寧にサポートします。】東武東上線上板橋駅 北口より徒歩約5分程の距離にあり、駅から近いためご家族様がお越しいただく際も便利です。 周辺には平和公園や城北中央公園と大きな公園が...

【特徴1】2020年3月オープン。住み慣れた街で、こだわりの食材を使用した四季折々のお食事と、ルーレットや麻雀などの大人の愉しみを活かした「明日が待ち遠しくなる暮らし」の提案を、お一人おひとりに寄りそいながらサポ...


東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線の3線利用可能という抜群のアクセスを誇る街、成増。活気に溢れる駅にほど近く、また広大で緑豊かな「光が丘公園」などにも隣接した、街と緑が共存する魅力的なロケーションに「応...
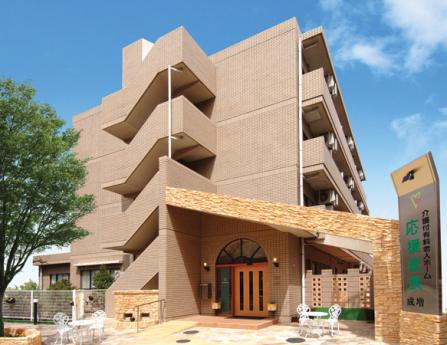


【相談員による月1回の面談、安心安全を叶える設備が連携】■駆けつけサービス 生活リズムの変化をセンサーが見守り、緊急時には警備会社ガードマンが駆けつけます。 ■看護師による健康相談(電話) 365日24時間、相談ボ...

東武東上線「上板橋」駅が最寄り、学生の活気ある声が聞こえる緑豊かな住宅街「板橋区中台」に木下の介護 介護付有料老人ホーム「リアンレーヴ上板橋」はございます。木下の介護ブランドにおける板橋区内5棟目のホームとし...

未来のオリンピック選手を養成するトレーニングセンターなど、国立のスポーツ関連施設から最寄りの「本蓮沼」駅より徒歩3分の位置に、木下の介護 介護付有料老人ホーム「リアンレーヴ板橋」はございます。ゆったりとした時...


見晴しの良い高台に位置し、陽光に溢れ明るい雰囲気の「ライフコミューン上板橋」。施設周辺には散歩に適した大きな公園や買い物に便利な大型スーパーもあり、恵まれた環境が魅力です。趣向を凝らしたイベントやレクリエー...

【2018年7月OPEN!「和」をテーマとした安らぎのホーム】クラーチ・ファミリア小竹向原は、日本ならではの「和」をテーマとした外観・内装にこだわった有料老人ホームです。開放的なエントランスを抜けると、和デザインで溢...

【医療法人が運営する施設。 医療ニーズが高い方もご入居可能】オリヴィエ前野町は2020年10月1日開設の介護付有料老人ホームです。 外出や外泊、居室での面会も可能となっています。 中心静脈栄養・経管栄養・インスリン...

【■がん末期・神経難病に特化したホスピス住宅です。】【2つの専門性~メディカルを活かしたケア~】 1・がん末期のケア 専門スタッフの丁寧なサポートのもと、 適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、ご入居者様お...


はじめての老人ホーム探し。知識がなければどんな基準で選ぶべきか悩んでしまいます...

失敗しない老人ホームを選ぶには施設見学が欠かせません。「施設の雰囲気」や「設備...

老人ホーム選びの基準はさまざまです。費用や場所、介護サービス、看取りなどのすべ...

有料老人ホームの費用を詳しく解説。介護付きと住宅型の料金の違い、入居一時金、月...
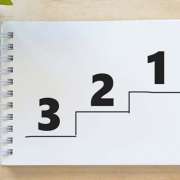
老人ホームを探して入居するまでの流れを解説。入居までに行うことは意外と多く、時...

有料老人ホームでは入居一時金が高額になることも。高い初期費用を払えない人には、...

ブランド・シリーズ
SOMPOケア ラヴィーレグラン
運営法人
SOMPOケア株式会社
ブランド・シリーズ
SOMPOケア そんぽの家
運営法人
SOMPOケア株式会社お客様の経済的状況や身体状況、
ご希望をお伺いし、
専任の入居相談員が
厳選した老人ホームをご案内します。
\お気軽にご相談ください/
入居者様や資料請求、見学予約など各種お問い合わせなど全て無料でご利用いただけます。
フリーダイヤル、メールにて相談員と直接相談が可能です。
オアシス介護では、施設経験のあるスタッフが実際の経験をもとに、施設での暮らしをイメージできるようお話しします。料金や地域だけでなく施設サービスの特徴を把握した上で施設をご紹介いたします。
有料老人ホームなどの高齢者向け住宅に特化して、ご相談や紹介、ご案内を行っている相談室です。
東京都の特徴と老人ホーム・介護施設の現状
世界最大規模の巨大都市圏、東京
日本の首都として、あるいは世界都市として誰もが知るのが、東京都です。人口は2023年4月の推計で1406万人ほどと、日本の総人口の1割以上を占めます。
実は、世界基準で東京という都市を見ると、都県境を超えて拡大しているのです。神奈川・埼玉・千葉だけでなく、茨城県や山梨県などの一部までもが、東京大都市圏に含まれます。
統計により数字の違いはあるのですが、いずれの統計でもこの域内の人口は3000万人を超えます。都市圏人口としては世界最大の、巨大都市圏の中心が東京なのです。
東京都内・都外アクセスも良好
巨大都市でもあり、政治経済の中心地でもある東京には、電車やバス、首都高速道路などの交通が整備されているので、どこに行くにも便利です。また、日本各地からの交通網も集中します。
このため、家族が老人ホームに面会に行く際にも交通面で困ることは少ないでしょう。
高速道路、新幹線などの高速鉄道は、東京から放射状によく整備されています。
国内線を主に担当する羽田空港からは、比較的距離がある各地の主要都市との便が、頻繁に発着しています。東京は、日本各地に行くことも、各地から来ることも非常に便利な都市です。このことが、東京という都市のある面での特性・特長を形成しています。
自治体ごとの老人ホーム整備状況
これだけの人口と富が集中する東京都ですが、老人ホームの現状はどのようになっているでしょうか。まず、全体のイメージを示します。老人ホーム・サ高住については、区部では世田谷区がもっとも多く、ついで練馬区、足立区、大田区、そして板橋区と江戸川区は同程度の順となっています。
区部は居住者も多いため、どこも老人ホームや介護施設数は多いのですが、千代田区、中央区といった、そもそもの人口が少なく、高齢者人口も他の地域に比べて少ない区に関しては、施設数は多くありません。
多摩地域では、市域人口の多い八王子市と町田市の多さが突出しています。ついで府中市、西東京市、青梅市、日野市など、多摩地域でも西側の自治体に施設が多い傾向があります。
東京都における施設種別ごとの整備状況
公的施設について東京都の統計を見ると、2023年8月時点で、特別養護老人ホームが区部に341施設、多摩地区に236施設、島しょ部に5施設あります。特別養護老人ホームは、区部より多摩地区および島しょ部において、人口に比較すると施設数が多くなります。
介護老人保健施設、いわゆる老健も区部に118施設、多摩地区に85施設あります。老健に関しては特養とは逆に、区部のほうに施設が多く立地していることがわかります。
また、軽費老人ホームやケアハウスについては、定員数や施設数は多くありませんが、区部への立地が多くなっています。近年では、都市型軽費老人ホームが増加しています。
グループホームは区部に498施設、多摩地区に221施設、島しょ部に1施設あります。グループホームの分布は、実際の人口比率にほぼ近い施設数であることがわかります。
東京都にまとまった施設数の統計データはありませんが、サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数は、区部では足立区・世田谷区・板橋区に、多摩地域では八王子市・町田市・立川市が多くなっています。人口の多い市区に、多く立地する傾向があるといえます。
なお、サービス付き高齢者向け住宅の数は、全国的に増え続けています。東京都も例外ではなく、新設も多くなっています。
有料老人ホームについても、多くの施設があります。介護付きと住宅型をあわせた数になりますが、2023年8月現在、有料老人ホームは区部に693施設、多摩地域に369施設、島しょ部(小笠原村)にも住宅型が1施設あります。開設予定の有料老人ホームも、同じ時点では35ほどあり、介護付きで定員が600名超という大きな施設もあります。
老人ホーム選びは、都内にこだわらないという選択も
ここまで見ると、人口が多い分、施設数も多いのが東京都である、と言うことができます。入居状況としては、全国各地で、特に特別養護老人ホームに関しては入所待ちが相次いでいるという問題がありますが、東京都ではどうでしょうか。
厚生労働省がまとめた、2022年4月時点での特別養護老人ホームの待機者数は、21,495人となります。施設定員に対しての空き待ちを示す比率は決して高くはないのですが、待機者の人数だけでいえば、2位となった神奈川県の14,238人を大きく上回っています。
状況は改善傾向にあるとはいえ、東京都での特別養護老人ホーム入所については、かなり厳しい状況であることがわかります。特養や有料老人ホームなどへの入所を希望する場合は、近隣県の施設を検討することも視野に入れるといいでしょう。
理由としては、地理・交通アクセスの利便です。区部在住の方の場合、多くの地域では、同じ都内とはいえ、施設数が多い多摩地域の西部より、千葉県や埼玉県、神奈川県といった隣接県のほうが、実際の距離もアクセス時間も、はるかに短くなるケースが多いのです。
また、高齢者には、地方出身で進学や就職のために上京した人も少なくはありません。人生の中で、東京以外の場所で過ごした時間がそれなりにあり、東京以外にも愛着がある場所を持つ人もいます。本人の希望が第一ですが、入所を希望する高齢者の出身地や、縁が深い地域にある施設を選択するのも、プランのひとつとして考えてもいいでしょう。
最初のほうで述べた通り、東京圏の交通網は、非常に高度なレベルで整備がされています。近隣県との往来はもちろん、遠隔地でも、たとえば県庁所在地クラスの都市であれば、日帰り往復も可能なほどに整備されています。
選択の幅が広い有料老人ホーム
また、東京都は有料老人ホームが多いことも特徴です。平均所得が高いということは、富裕層も多く住んでいることを意味します。それなりの費用を負担しても、快適な老後を過ごしたいと考える高齢者にとっては、豪華な設備や手厚いサポートを受けられる施設の選択肢が多い東京都は、非常に魅力的に映るでしょう。
なお、有料老人ホームに関しては、月額の施設利用料や、入居一時金の差が大きくなります。設備についても、施設ごとに特徴が大きく異なります。有料老人ホームとはいえ、リーズナブルな価格で利用できる施設も、探せばあるものです。
また有料老人ホームなら、こだわりやゆずれない条件、入居する高齢者の身体状態に適した施設を選ぶことも可能です。多くの有料老人ホームでは認知症に対応していますし、肝炎や結核などの症状があっても医療処置を行なえる施設も多数あります。
オアシス介護掲載の有料老人ホームでは、ターミナルケアを行なっている施設は8割以上と、他の都道府県に比べても高い傾向です。また、2人部屋を用意している施設も多いので、夫婦での入居も検討しやすくなっています。
東京都の高齢者の状況
さて、東京都における高齢者の人口は2022年9月の推計で、312万人となっています。高齢化率は23.5%で、いずれも過去最高を更新しました。2022年の全国平均が29.1%ですから、それよりは低い値です。しかし、超高齢社会の世界基準である21%は既に上回っています。
なお、東京都でも今後、高齢者人口は増加し、比率は上昇していくことが見込まれています。出生数が非常に多い団塊の世代は、既に高齢者の仲間入りを果たしていますが、今後も出生数が多い世代が高齢者になっていくからです。既に、高齢者人口の増加数は、東京都がトップになっています。
高齢化に伴い、高齢者世帯も増えています。2000年からは、高齢者の単独世帯が高齢者の夫婦世帯を数で上回り、その傾向は続いています。将来的には、高齢者の単独世帯が100万を超えると予測されています。
なお、東京都における要介護認定者数(要支援を含む)も増加傾向にあり、2012年に約46.4万人だった要介護認定者は、2018年になると59万人に増えました。6年で13万人近く増加したことになります。今後も要介護認定者は増えることが見込まれています。
東京都では賃貸住宅で暮らす高齢者も多い
さて、東京都の住宅事情として、持ち家比率が低く、民間の賃貸住宅の比率が高い傾向にあります。実はこのことにも注意が必要です。何らかの事情で賃貸住宅に住み続けることができなくなった場合、自立した生活を営めているうちでも、高齢者は転居が難しくなります。
何かあった時点で急いで老人ホームを探すと、確認不足のために後悔する事態になることもありえます。元気なうちに多くの老人ホームを見学して、目安をつけておくといざというときにも安心です。
なお、認知症を持つ高齢者がより自分らしく生きることを目標として、地域包括ケアシステムの構築が進められているのは、東京都でも同様です。拠点となる地域包括支援センターも数を増やしていますが、人口が多い分、どうしても1箇所のセンターあたりで対応する高齢者の人数が多くなっています。
また、地域包括ケアシステムを導入した際の課題として、地域社会が機能していることが求められます。対象となる高齢者が、近所付き合いなど、何らかのかたちで地域のコミュティの中にいる必要があります。
東京都の高齢者の社会参加
さて、東京都福祉保健局の調査によると、高齢者の近所付き合いについて「お互いに訪問しあう人がいる」はわずか18.9%に過ぎません。「立ち話をする程度の人がいる」が41.3%で最多、「あいさつをする程度の人がいる」が29.7%で、残る10.2%は「まったく近所付き合いがない」高齢者です。
砂漠にも模される、東京という土地柄を反映した結果と感じる方も多いでしょう。ただし、地域行事や趣味など、社会参加の機会が多いのが都市部の特徴ですし、25%もの高齢者が何らかの仕事に就いていますから、この近所付き合いの調査結果をもって、地域社会が機能していないと断じることはできません。
とはいえ、調査結果の重要性は、自治体も強く認識しています。さまざまなアプローチで、地域社会が再度機能するような試みが行われています。
世田谷区における地域包括ケアシステムの試みは、在宅医療や訪問介護サービスの質的な充実、高齢者の居場所と出番を創出するための取り組みを行うこと、介護予防を行うことを軸にしています。これなどは、大都市における先進的かつ模範的な取り組みであると、高い評価を受けています。
思った以上に広い「東京」
東京をイメージするものとして、多くの方からは、銀座・六本木・原宿といった繁華街や、新宿の高層ビル群、ランドマークでもある東京スカイツリーなど、近代的な大都市像が答えとして返ってくることでしょう。事実、そのイメージは正確なもので、世界最大規模でありながら、清潔な近代都市が東京です。
その一方で、秋川渓谷や高尾山といった、豊かな里山の自然も、東京都にはあります。また、温暖な気候に恵まれた伊豆諸島をはじめとした島しょ部には、亜熱帯気候でもある小笠原諸島までもが含まれます。あらためて見てみると、東京都が、想像以上に広大であることに驚かされます。
このように、地理的に東京都を語る場合は、23の特別区からなる「区部」とその西側に位置する「多摩地域」、さらには「島しょ部」と3つに分類することが多いです。
人口ベースでは区部が967万人、多摩地域が429万人、島しょ部が2.4万人ほどとなっています。老人ホーム・福祉施設なども、そのほとんどが区部および多摩地域に存在します。
東京という地域の特徴
現代の日本における政治・経済の中心地が東京であることは、疑いようのないところでしょう。文化面での発展もめざましく、国内主要メディアの多くは本拠地を東京に持っており、情報発信力が突出して高いことも、東京の特徴といえます。
東京には、東京都を地元とする人はもちろん、地方出身者も多く集まります。先祖代々その場所に住む人、新しくやってきた人。さまざまなルーツを持つ人たちが隣り合いながら暮らしているのが、東京の区部、そして多摩地域といった、都市化が進んだエリアの特徴です。
なかには、介護が必要になった親に自分の近くで暮らしてほしいと、東京で老人ホームを探す地方出身者もいることでしょう。
また、特筆すべきは、平均所得の突出した高さです。都民1人あたりの平均所得は2014年度で451万円と、2位となった愛知県の353万円を、大きく上回っています。
全国平均は306万円弱で、埼玉、千葉、神奈川といった東京の隣接県を含め、300万円に届かない道県のほうが、圧倒的に多いのです。
平均所得が多いぶん地価も高い東京都では、有料老人ホームにかかる費用も高めの傾向です。ですが、東京都には高級志向の老人ホームからリーズナブルな老人ホームまで揃っているので、選びやすい環境といえるでしょう。